「夢の新築一戸建てを手に入れたけれど、固定資産税って一体いくらかかるんだろう…?」そんな不安を感じていませんか?
そんな不安を持つ方に向けて、税金の基礎知識から具体的な計算方法、そして損をしないための注意点まで徹底解説します。
将来の税額がどう変わるのか、賢く固定資産税を抑えるための方法もご紹介。
新築ならではの軽減措置を最大限に活用し、賢くマイホームを維持していくための情報が満載です。
さらに、もし「新築」だけでなく「リノベーション」という選択肢も視野に入れているなら、理想の住まいを叶える【フルリノ!】で、あなたにぴったりのリノベ会社を見つけてみませんか?
賢く家づくりを進めるための第一歩を、この記事とフルリノ!がお手伝いします。
<<cta-line-01>>
新築一戸建ての固定資産税、計算方法
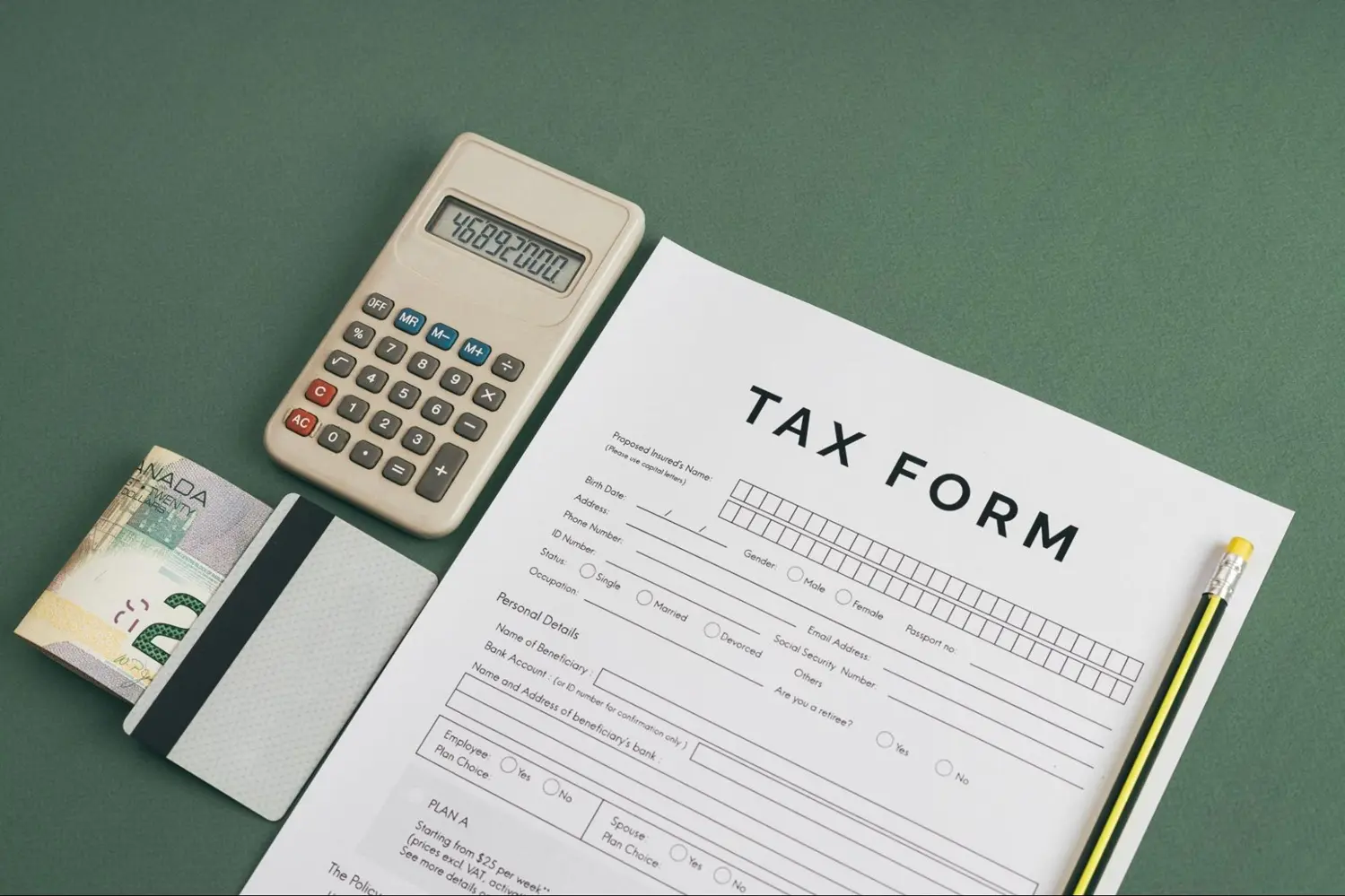
新築一戸建ての固定資産税がどのように計算されるのか、仕組みを知っておくことは、納税額を予測し、資金計画を立てる上で重要です。
固定資産税の計算に必要な固定資産税評価額と固定資産税の税率を詳しく解説します。
固定資産税評価額
固定資産税の計算の土台となるのが固定資産税評価額です。
市区町村が固定資産(土地や家屋)の適正な時価に基づいて決定するもので、原則として3年に一度見直しが行われます。
新築一戸建ての場合、土地と建物それぞれに評価額が定められます。
土地の評価額の算出方法
土地の固定資産税評価額は、主に路線価方式によって算出されます。
路線価とは、道路に面した土地の1平方メートル当たりの価格のことで、国税庁が毎年公表する「路線価図」で確認できます。
路線価を基に、土地の形状や面積、利用状況などの要素を考慮して、個々の土地の評価額が決定されます。
建物の評価額の算出方法
建物の固定資産税評価額も、原則として3年に一度見直されます。
主な評価方法として再建築価格方式が用いられます。
再建築費とは、もし今、全く同じ建物を新しく建てるとしたら、どれくらいの費用がかかるかの概算の金額です。
再建築費を基準として、建物の建築年からの経過年数に応じて価値が減少していく分を差し引いて、評価額が算出されます。
建物の構造や使われている材料、設備のグレードなどによって、再建築費は大きく異なります。
固定資産税の税率
固定資産税の税率は、原則として市区町村が条例で定めることになっていますが、多くの自治体では標準税率である1.4%を採用しています。
ただし、自治体の財政状況などによっては、標準税率とは異なる税率が適用される場合もあるため、お住まいの地域の税率を確認が重要です。
税率は、自治体のウェブサイトや窓口で確認できます。
固定資産税額を計算してみよう
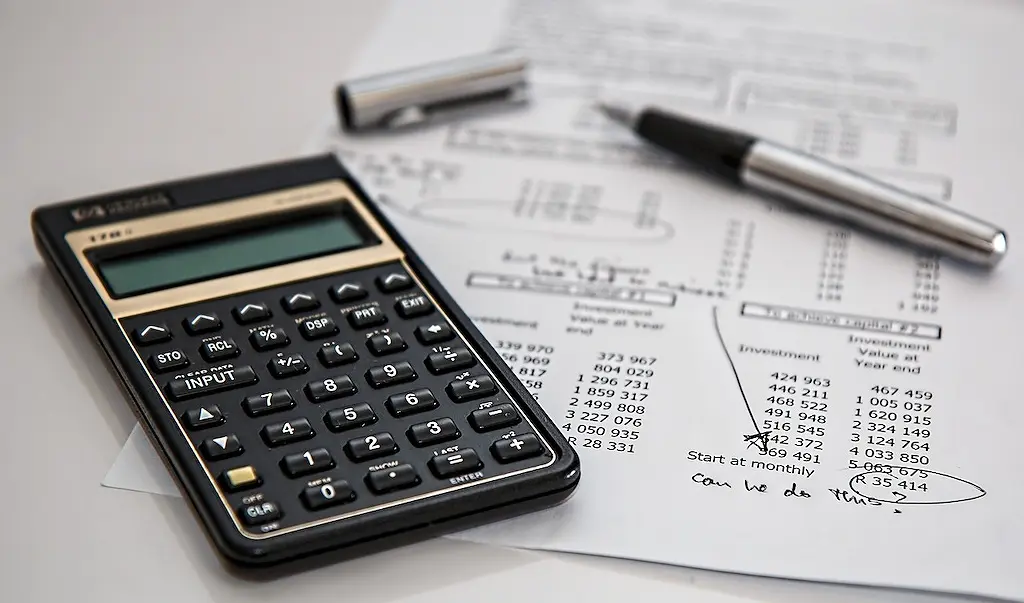
固定資産税額は、以下の計算式で算出されます。
固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 税率
言葉だけだと少し難しく感じるかもしれませんが、仕組みは意外とシンプルです。
実際に新築一戸建ての固定資産税がどのくらいになるのか、具体的なケースを想定して一緒に計算してみましょう。
評価額3000万円の新築一戸建ての場合
例えば、土地の評価額が1800万円、建物の評価額が1200万円、合計で3000万円の新築一戸建てを例に見ていきましょう。(固定資産税率は標準の1.4%、都市計画税率は0.3%とします)
ここで、税額を大きく左右する2つの重要ポイントがあります。
- 建物には「新築住宅の軽減措置」が適用される(最初の3年間、固定資産税が半分に!)
- 土地には「住宅用地の特例」が適用される(税金の計算のもとになる評価額が大幅に割引される!)
この制度をしっかり理解しているかどうかが、将来の納税額のイメージを掴むカギになります。
では、さっそく計算してみましょう!
【1年目~3年目】軽減措置で税額が最もおトクな期間
新築ならではのメリットを最大限に受けられる3年間です。
- 土地の税金(固定資産税+都市計画税)
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、税負担が大きく軽減されます。
評価額そのものが下がるわけではありませんが、税額を計算する際の基礎となる金額(課税標準額)が、実際の評価額の6分の1や3分の1までぐっと低くなるのです。
- 固定資産税: (1,800万円 × 1/6※) × 1.4% = 4.2万円
- 都市計画税: (1,800万円 × 1/3※) × 0.3% = 1.8万円
【土地の合計】 年間6万円
※小規模住宅用地(200㎡以下)の特例を適用
- 建物の税金(固定資産税+都市計画税)
床面積が50㎡以上280㎡以下という一定の条件を満たす新築住宅について、新たに固定資産税が課税される年度から3年間、家屋にかかる固定資産税額が2分の1に減額されます。(マンションの場合は5年間)
- 固定資産税: (1,200万円 × 1.4%) × 1/2 = 8.4万円
- 都市計画税: 1,200万円 × 0.3% = 3.6万円 (※都市計画税は軽減されません)
- 【建物の合計】 年間12万円
▶︎ 1年目~3年目の合計年税額 土地(6万円)+ 建物(12万円)= 年間 約18万円
【4年目以降】軽減措置が終了した後の税額
4年目からは建物の軽減措置がなくなるため、税負担が少し上がります。このタイミングを知っておくことが大切です。
- 土地の税金:年間 約6万円 (3年ごとの評価替えで見直されますが、ここでは同額とします)
- 建物の税金
半額だった建物の固定資産税が、本来の税額に戻ります。
- 固定資産税: 1,200万円 × 1.4% = 16.8万円
- 都市計画税: 1,200万円 × 0.3% = 3.6万円
【建物の合計】 年間20.4万円
▶︎ 4年目以降の合計年税額 土地(6万円)+ 建物(20.4万円)= 年間 約26.4万円
4年目に税額が上がることをあらかじめ知っておけば、家計の計画も立てやすくなります。
ただし、これはあくまでシミュレーションです。
実際には、建物の評価額は年数の経過とともに少しずつ下がっていくため、4年目以降の税額もこの金額から緩やかに減少していくのが一般的です。
ご自身の物件の正確な税額は、毎年市町村から送られてくる納税通知書で必ず確認するようにしましょう。
土地のみを所有している場合、土地のみの固定資産税
もし建物がまだ建っていない土地のみを所有している場合、課税対象となるのは土地のみです。建物がないため、新築の軽減措置は適用されません。
例えば、土地の固定資産税評価額が1000万円の場合、標準税率1.4%で計算すると、固定資産税額は14万円となります。
都市計画税も同様に課税されます(税率が0.3%の場合、3万円)
【評価額別】新築一戸建ての固定資産税、税額の目安

ご自身の新築一戸建ての固定資産税がどのくらいになるかの目安を知りたい方も多いでしょう。
ここでは、評価額別に固定資産税額の目安をシミュレーションしました。
以下の税額は、「土地評価額:建物評価額=6:4」「土地面積は200㎡以下」という特定のモデルケースで計算したものです。
実際の税額は物件の条件によって変動するため、あくまで大まかな目安としてご活用ください。(都市計画税は含んでいません)
評価額 | 新築軽減措置適用時(3年間) | 4年目以降 |
2000万円 | 約8.4万円 | 約14万円 |
3500万円 | 約14.7万円 | 約24.5万円 |
4000万円 | 約16.8万円 | 約28万円 |
5000万円 | 約21万円 | 約35万円 |
6000万円 | 約25.2万円 | 約42万円 |
7000万円 | 約29.4万円 | 約49万円 |
8000万円 | 約33.6万円 | 約56万円 |
あくまで概算であり、実際の税額は自治体の税率や個々の物件の評価額によって異なります。
建物の評価額は年々緩やかに減少していくため、実際には記載の金額から変動する可能性があります。
ご自身の物件の正確な税額は、毎年送られてくる納税通知書で確認するようにしましょう。
新築一戸建ての固定資産税を安く抑えるには
.webp)
新築一戸建ての固定資産税は、長く付き合っていく税金だからこそ、できるだけ負担を減らしたいと考えるのは当然のことです。
本項では新築住宅ならではの軽減措置を最大限に活用する方法や、その他の減税制度・特例措置を解説します。
新築住宅の軽減措置を最大限に活用する
新築住宅に適用される固定資産税の軽減措置は、税負担を大きく軽減してくれる重要な制度です。内容をしっかりと理解し、最大限に活用しましょう。
軽減措置の概要
新築住宅の軽減措置とは、新たに建てられた住宅の固定資産税が、一定期間減額される制度です。
居住用住宅の取得を促進し、居住者の負担軽減を目的としています。
軽減されるのは家屋の固定資産税であり、土地の固定資産税や都市計画税は対象外となる点に注意が必要です。
適用条件
新築住宅の軽減措置を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。
- 床面積の要件: 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 自己居住用: 原則として、納税義務者本人が居住している住宅であること。
- 併用住宅の場合: 店舗や事務所などと併用している住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
条件を満たさない場合、軽減措置は適用されませんので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
軽減期間と軽減額
軽減期間と軽減額は、住宅の種類によって異なります。
住宅の種類 | 減額期間 | 減額割合 | 備考 |
戸建て住宅 | 3年間 | 2分の1 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から |
共同住宅(マンションなど) | 5年間 | 2分の1 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から |
長期優良住宅 (戸建て) | 5年間 | 2分の1 | 耐震性や省エネ性能などが一定の基準を満たす長期優良住宅として認定された場合 |
長期優良住宅 (共同住宅) | 7年間 | 2分の1 | 耐震性や省エネ性能などが一定の基準を満たす長期優良住宅として認定された場合 |
ご自身の住宅の種類を把握し、どのくらいの期間軽減措置が適用されるのかを確認しておきましょう。
その他の減税制度・特例措置
新築住宅の軽減措置以外にも、固定資産税を安く抑えるための制度があります。該当する可能性がある場合は、積極的に活用を検討しましょう。
住宅の省エネ性能を高める(長期優良住宅など)
前述の通り、長期優良住宅の認定を受けることで、固定資産税の軽減期間が延長されるメリットがあります。
長期優良住宅とは、耐震性、省エネルギー性、維持管理の容易性、住戸面積、居住環境、維持保全計画などの複数の項目で、一定の基準を満たす住宅のことです。
認定を受けるためには、建築前に申請が必要となるため、新築の計画段階から検討をおすすめします。
その他の特例措置や減税制度の例
改修の種類 | 概要(固定資産税減額) |
耐震改修 | 一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。 |
バリアフリー改修 | 高齢者や障がい者の方が居住する住宅で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。 |
省エネ改修 | 一定の省エネ改修工事を行った場合にも、固定資産税が減額されます。 |
特例措置や減税制度は、適用期間や減額幅、適用要件などが細かく定められています。
詳細はお住まいの市区町村の税務担当課に問い合わせるか、自治体のウェブサイトで確認するようにしましょう。
固定資産税評価額を確認する
固定資産税額は、固定資産税評価額に基づいて計算されます。
もし、評価額に疑問がある場合は確認してみましょう。節税につながる可能性があります。
評価額に疑問がある場合
固定資産税評価額は、毎年4月頃に送付される納税通知書で確認できます。
もし、評価額が急に上がっていたり、近隣の似たような物件と比べて明らかに高いと感じた場合は、いくつかの方法で確認してみましょう。
お住まいの市区町村の税務担当課で固定資産課税台帳を確認することができます。
ここでは、ご自身の土地や家屋の評価額だけでなく、場合によっては近隣の物件の評価額も確認できます。
また、評価額の算出根拠や内訳について、税務担当課に問い合わせてみるのも有効です。
もし、これらの確認をしても評価額に納得がいかない場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出を検討しましょう。
ただし、この申し出には期限があるため注意が必要です。
固定資産税評価額は、原則として3年に一度、見直し(評価替え)が行われ、その年度には土地や建物の市場価格の変動などが評価額に反映されることがあります。
そのため、評価替えのタイミングで評価額が大きく変動することも考えられます。
もし評価額に疑問を感じたら、まずは自治体に問い合わせて評価の根拠を確認することをおすすめします。
固定資産税を安く抑える方法は以下の記事でも解説しています
一戸建ての固定資産税はいくらかかる? 平均額や軽減措置・安く抑える方法3選を解説【2024年】
【年数別】新築一戸建ての固定資産税、税額の目安
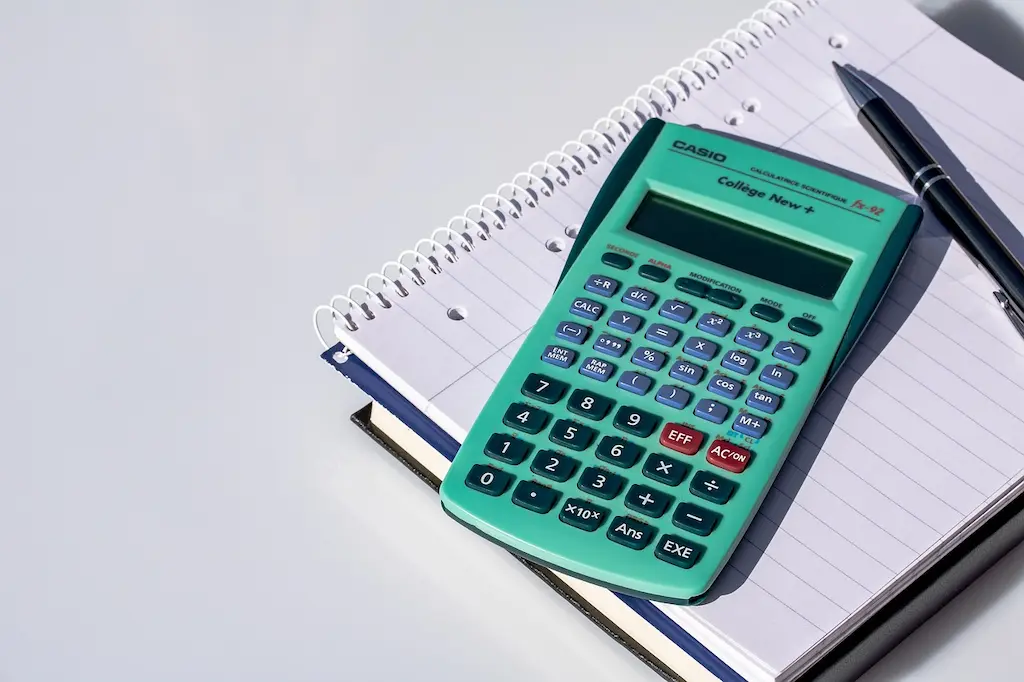
新築時の固定資産税は軽減措置によって抑えられますが、その期間が終了すると税額はどのように変化するのでしょうか。
新築時と軽減措置期間終了後の税額の目安を年数別に見ていきましょう。
新築時の税額(軽減措置適用)
新築住宅の軽減措置が適用される最初の3年間(戸建て住宅の場合)は、固定資産税額が2分の1に減額されます。
評価額3000万円の住宅の場合、固定資産税額は通常42万円ですが、この期間は21万円となります(都市計画税は別途かかります)
4年目の固定資産税(軽減措置終了後の変化)
戸建て住宅の場合、4年目からは新築軽減措置が終了するため、固定資産税額は本来の額に戻ります。上記の例であれば、固定資産税額は42万円です。
都市計画税は引き続き課税されます。
このタイミングで、税負担が大きく増えることを認識しておきましょう。
6年目の固定資産税
6年目の固定資産税は、基本的には4年目と同じ税額になります。
ただし、土地の価格変動や建物の経年による評価額の減少などがあれば、税額も多少変動する可能性があります。
一般的には、建物の評価額は年々緩やかに減少していく傾向にあります。
.webp)
10年目の固定資産税
10年目になると、新築時からさらに年数が経過し、建物の評価額もいくらか減少していると考えられます。
土地の評価額は、市場動向によって変動する可能性があります。
したがって、10年目の固定資産税額は、新築時や4年目と比較して、若干低くなることが一般的です。ただし、大幅な減少は見込めない場合が多いでしょう。
固定資産税の納付方法と時期
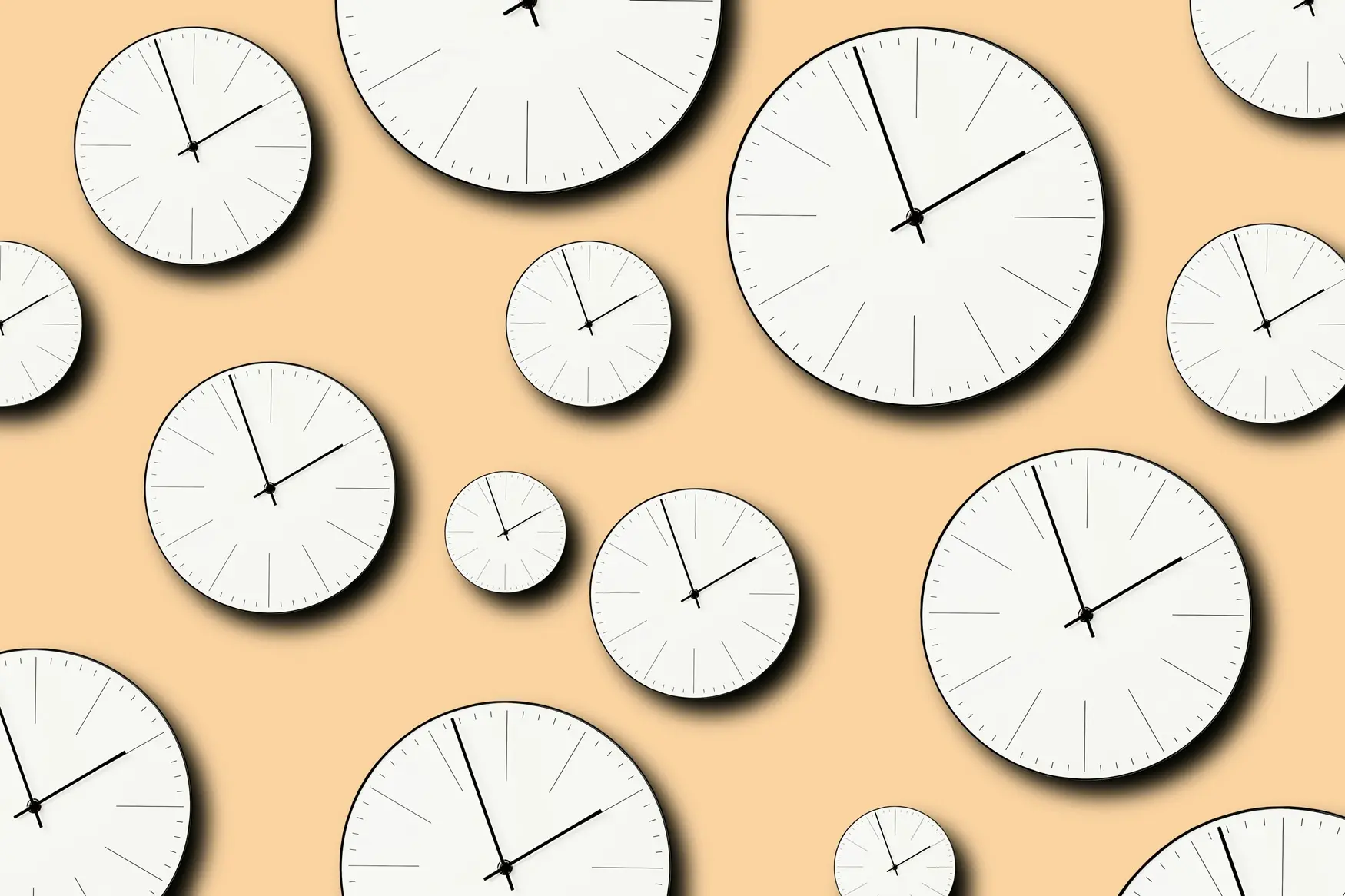
固定資産税は、年に数回に分けて納付するのが一般的です。本項では納付方法と時期を解説します。
年4回の分割納付が一般的
固定資産税は、通常、年4回に分けて納付します。
納付時期は自治体によって異なりますが、一般的には6月、9月、12月、翌年の2月頃に設定されていることが多いです。
各期ごとの納付金額は、年間の税額を4等分した金額になります。
一括納付のメリット・デメリット
分割納付の他に、年間の固定資産税額を一括で納付も可能です。
- メリット: 納め忘れを防ぐことができる、自治体によっては早期納付による割引制度がある場合も。
- デメリット: 一度にまとまった金額が必要になるため、資金計画によっては負担が大きい場合も。
ご自身のライフスタイルや資金計画に合わせて、納付方法を選ぶと良いでしょう。
納付方法
固定資産税の主な納付方法には、以下のようなものがあります。
支払い方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
口座振替 | 自動引き落とし | 納め忘れなし、手続き一度のみ | 事前登録必須、残高不足で引き落とし不可 |
納付書払い | 窓口で支払い | 手軽に支払い可能、現金払い対応 | 納付の手間、場所・時間に制限あり |
クレジットカード払い | ネット等でカード決済 | 自宅で手軽、ポイント付与、分割払い可(場合による) | 手数料発生の場合あり、利用限度額、システム障害の可能性 |
スマートフォン決済 | アプリで支払い | 自宅で手軽、ポイント付与、領収書データ管理(アプリによる) | 対応自治体限定、アプリ設定必要、チャージ残高必要 |
ご自身の都合の良い納付方法を選びましょう。

固定資産税はいつ納付するのか
具体的な固定資産税の納付期限は、自治体によって異なります。
通常、納税通知書に各期の納付期限が記載されています。必ず確認するようにしましょう。
納付期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生する場合があるので、期限内の納付を心がけてください。
中古物件とマンションの固定資産税はどうなる?新築との違い

新築一戸建ての固定資産税を解説してきましたが、中古物件やマンションの場合はどうなるのでしょうか。新築との違いを見ていきましょう。
新築との違い
中古物件の固定資産税評価額は、新築時に比べて低く設定されることが一般的です。建物の経年劣化が考慮されるためです。
また、新築のような固定資産税の軽減措置は、原則として適用されません。
ただし、一定の要件を満たす中古住宅の取得やリフォームを行った場合には、特例措置が適用されることもあります。
中古物件の築年数による評価額の変化(築40年、50年の物件)
中古物件の場合、築年数が経過するほど建物の評価額は大幅に下がっていきます。
特に、築40年、50年の物件になると、建物の評価額はほぼゼロに近い金額になることもあります。
そのため、固定資産税の負担は新築物件に比べてかなり低くなる傾向があります。
ただし、土地の評価額は築年数に関わらず評価されるため、土地の価格が高いエリアでは、一定の税負担が生じることもあります。
築50年の物件の固定資産税について、以下の記事で詳しく解説しています。
マンションの固定資産税
マンションの固定資産税は、一戸建てとは少し異なる仕組みになっています。
マンション全体の土地の評価額は、各戸の専有面積の割合に応じて按分され、それぞれの区分所有者に課税されます。
建物の評価額は、専有部分と共用部分の価値を合算して算出され、専有面積に応じて按分されます。
新築マンションにも軽減措置は適用されますが、戸建て住宅よりも適用期間が長いのが特徴です(原則として5年間)
<<cta-private-01>>
【番外編】中古物件を買ってリノベーションすれば、理想の住まいと賢い税金対策が両立できるかも
.webp)
新築一戸建ては魅力的ですが、固定資産税の負担が気になる方もいるかもしれません。
そんな方におすすめしたいのが、中古物件を購入してリノベーションする選択肢です。
中古物件の固定資産税は新築より安い?
中古物件の最大のメリットの一つは固定資産税が新築に比べて安いことです。
上述の通り、築年数が経過した建物は評価額が大幅に減少するため、固定資産税の負担を抑えることができます。
土地の評価額は新築と変わりませんが、建物部分の税負担が軽減されるだけでも、年間の支払い額は大きく変わってきます。
リノベーションで理想の住まいを実現する
中古物件の購入費用とリノベーション費用を合わせても、新築物件を購入するよりも費用を抑えられる場合があります。
そして、リノベーションなら、間取りや内装、設備などを自分の理想通りに作り上げることができます。
新築ではなかなか見つからない個性的な物件をベースに、自分だけのこだわりの住まいを実現できるのが、リノベーションの大きな魅力です。
リノベーションと新築について、以下の記事で詳しく解説しています。
リノベーションと新築はどっちがお得?違いやメリット・デメリットを解説!
<<cta-info-01>>
リノベーションを考えているならフルリノ!で探そう
もしあなたが固定資産税の負担を抑えつつ、理想の住まいを手に入れたいと考えているなら、中古物件のリノベーションという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
リノベーションには、新築にはない魅力がたくさんあります。しかし、どのリノベ会社に依頼すれば良いか迷ってしまうこともあるでしょう。
そんなあなたにおすすめなのが、リノベーションのポータルサイト「フルリノ!」です。
フルリノ!では、あなたの理想の住まいづくりをサポートする多くのリノベ会社と、豊富な施工事例を掲載しています。
リノベーションで後悔しないためには、多くの企業や事例を比較検討し、自分にぴったりの依頼先を見つけることが重要です。
あなたもフルリノ!で、賢く理想の住まい探しを始めてみませんか?
この記事を参考に、新築一戸建ての固定資産税の理解を深め、賢い住まい選びに役立ててください。
<<cta-consult-01>>









