固定資産税って、持ち家だと毎年かかるお金だけど、一体いくらになるんだろう?
特に築50年の一戸建ては、他の家と比べて税金はどう違うのか、賢く税金を抑える方法はあるのか気になりますよね。
この記事では、そんな疑問を徹底解説!
さらに、フルリノ!を活用すれば、リノベーションによる固定資産税の減税措置も期待できるかもしれません。
ぜひ最後まで読んで、あなたの疑問を解決し、住まいにかかるお金についてもっと詳しくなりましょう。
<<cta-line-01>>
固定資産税とは?
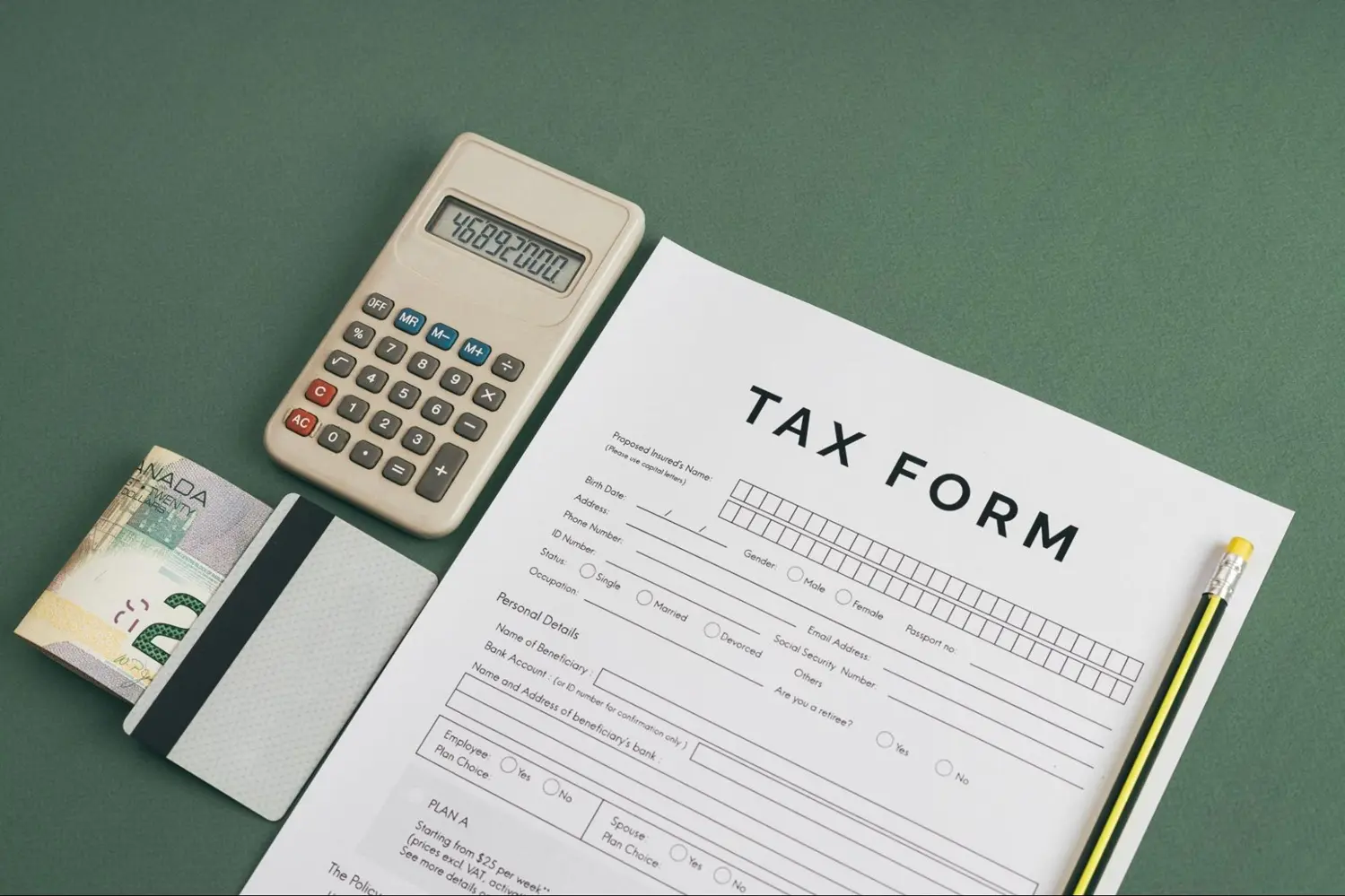
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を持っている人が、価値に応じて毎年納める税金のことです。
納められた固定資産税は、地域社会を支える様々な公共サービス(教育、福祉、消防活動など)の運営費用として活用されています。
固定資産税は、主に土地と家屋に対して課税され、固定資産の所有者は年1回、価値に応じた税金を納める義務があります。
納税の時期は自治体によって異なりますが、一般的には年4回に分けて納付することが多いです。
税額は資産の評価額で決定
固定資産税の税額は、固定資産の「固定資産評価額」に基づいて決定されます。
固定資産評価額とは、国が定めた基準をもとに、市町村が土地や建物の現在の価値を評価する金額のことです。これが固定資産税を計算するための基準となります。
土地の場合は、公示地価の7割を目安に評価額が決定され、家屋の場合は、再建築価格を基準に、建築後の経過年数に応じた減価償却を考慮して評価額が算出されます。
固定資産評価額は、原則として3年に一度見直し(評価替え)が行われます。
【さらに詳しく】
固定資産税の仕組みや評価方法の全体像は、総務省の公式ページで確認できます。
固定資産税は住居の種類によってどう違うの?

固定資産税は、住居の種類によって計算方法や税額に違いがあります。一戸建て、マンション、中古住宅、それぞれ見ていきましょう。
一戸建ての固定資産税
一戸建ての固定資産税は、土地と建物それぞれに課税されます。
土地の評価額は、土地の地価に基づいて計算します。
一般的に、土地の固定資産税は地価の影響を受けやすいです。
建物は、年数が経つにつれて価値が下がると考えられており、この価値の減少を減価償却といいます。
固定資産税の評価額を計算する際に、建築費用から減価償却分が差し引かれます。つまり、築年数が古いほど、建物の固定資産税は安くなる傾向があります。
固定資産税の平均額
一般的に、一戸建て住宅の固定資産税は年間10万~15万円程度が目安とされています。
一方で、分譲マンションの場合は8万~12万円ほどになるケースが多いです。
ただし、税額は建物の構造や築年数、所在地といった条件に大きく左右されます。
実際には各自治体から届く納税通知書の内容を確認するのが確実です。
一戸建ての固定資産税の計算方法や軽減措置について、さらに詳しく
マンションの固定資産税
マンションの固定資産税も、土地と建物それぞれに課税されますが、土地の評価額はマンション全体の土地の評価額を、各戸の専有面積の割合に応じて按分して計算されます。
一般的に、マンションは一戸建てに比べて土地の持ち分が少なくなるため、土地の固定資産税は一戸建てよりも安くなる傾向があります。
建物の固定資産税は、専有部分の評価額に共有部分の評価額を按分したものが課税対象となります。
中古住宅の固定資産税
中古住宅の固定資産税は、新築住宅に比べて評価額が安くなるため、税額も低くなる傾向があります。
これは、建物が築年数の経過とともに減価償却されるためです。
ただし、中古住宅を購入後にリフォームやリノベーションを行った場合、内容によっては建物の評価額が上がり、固定資産税が増額になる可能性もあります。
リノベーションと固定資産税について、以下の記事で詳しく解説しています。
リノベーションで固定資産税が上がる?抑える方法と築年数別のベストタイミング
固定資産税評価額の経年変化と下落の仕組み
固定資産税の基準となる評価額は、建物の経年劣化を考慮して毎年見直されます。新築時の評価額を100%とした場合、最初の1年が経過すると、その価値は約80%にまで大きく減少します。
その後も建物の価値は年々下がり続けますが、その下落のペースや最終的な到達点には特徴があります。特に、木造住宅のように再建築費区分が比較的低い建物では、新築から約15年で評価額が最小値の20%に達するのが一般的です。
この「最小値20%」というのは、建物の構造に関わらず適用される補正率の最低値です。つまり、どんなに古い建物であっても、固定資産税の評価額が新築時の20%を下回ることはありません。これは、建物が存在する限り、一定の資産価値があるとみなされるためです。
このように、固定資産税の評価額は、築年数によって大きく変動し、最終的には一定の基準値に落ち着くことを理解しておくことが、長期的な税負担を考える上で重要になります。
土地にかかる固定資産税の計算方法

土地にかかる固定資産税は、どのように計算されるのでしょうか。土地の評価額の決まり方と、具体的な計算方法を見ていきましょう。
土地の評価額はどう決まるのか
土地の価値は、固定資産税を計算するために、毎年見直されます。その基準となるのが公示地価で国土交通省が発表する、その年の土地の価格です。
固定資産税の評価額は、公示地価のおおよそ7割を目安に決まります。
また、土地の形や広さ、道路との関係なども考慮されます。
地域によっては、路線価という道路に面した土地の価格を基準に評価する場合もあります。
土地の固定資産税の計算方法
土地の固定資産税は、以下の計算式で求められます。
固定資産税額(土地) = 固定資産税評価額(土地) × 税率
固定資産税の税率は、原則として1.4%ですが、市町村によって異なる場合があるので必ず確認しましょう。
住宅用地は、課税標準額を減額する特例措置(小規模住宅用地:200㎡以下は評価額の6分の1、一般住宅用地:200㎡超は評価額の3分の1)があります。
築50年の一戸建ての固定資産税はいくら?築年数と税の関係

築50年の一戸建ての固定資産税は、多くの方が気になるポイントです。
築年数と固定資産税の関係を詳しく見ていきましょう。
まずはシミュレーション!築50年の一戸建ての固定資産税を概算で計算してみよう
築50年の一戸建ての固定資産税を正確に算出するには、土地と建物のそれぞれの固定資産税評価額を把握する必要があります。
ここでは概算で計算してみましょう。
【例】東京都の平均的な固定資産税率で計算してみよう
仮に、東京都にある平均的な一戸建てで、固定資産税率を1.4%として計算してみます。
土地
固定資産税評価額:4,500万円 × 70% = 3,150万円
課税標準額(1/6特例適用):3,150万円 × 1/6 = 525万円
土地の固定資産税:525万円 × 1.4% = 73,500円
建物
建物の固定資産税評価額:50万円
建物の固定資産税:50万円 × 1.4% = 7,000円
合計:80,500円/年
以下の表は、さまざまな条件における固定資産税額の目安です。
状況 | 固定資産税額の目安 |
一般的な築50年戸建 | 1~2万円 |
土地100㎡・評価高め | 8万円台 |
立地・土地が特に良い | 10万円超 |
築50年の一戸建てにかかる年間固定資産税は、建物や土地の評価額、所在地、市町村の税率によって異なりますが、おおよそ4万円〜7万円が一般的な目安です。立地が良いエリアでは10万円を超えることもあります。
なお、分譲マンションの場合は、専有部分に加えて土地の共有持ち分にも課税されるため、一戸建てよりもやや高額になる可能性があります。
【関連情報】
築30年の一戸建ての固定資産税について詳しく知りたい方はこちら
木造住宅の固定資産税の特徴
木造住宅は、他の構造の建物(鉄骨造や鉄筋コンクリート造など)よりも耐用年数が短いため、減価償却が早く進む傾向があります。
築50年になると、建物の評価額は新築時に比べてかなり低くなることが一般的です。
田舎の固定資産税について
一般的に、田舎(都市部以外)の土地は都市部に比べて地価が低い傾向にあるため、土地の固定資産税評価額も低くなることが多いです。
ただし、固定資産税率は市町村によって異なるため、必ずお住まいの地域の税率を確認することが重要です。
築年数と固定資産税の関係:築浅の家と築50年の家で税額はどう違う?
建物の固定資産税評価額は、新築時から年数の経過とともに、建物の種類や構造によって定められた耐用年数に応じて減価償却によって徐々に下がっていきます。
そのため、築浅(例えば築30年や40年)の家は、築50年の家に比べて一般的に評価額が高くなり、固定資産税も高くなる傾向があります。
さらに築年数が経過し、築60年~80年になると、建物の評価額はさらに安くなることが考えられます。
ただし、建物の状態やメンテナンスの状況によって評価額は変動する場合があります。
固定資産税の評価替え時期:築6年目と10年目の税額変動に注意
固定資産税は、原則として3年に一度、評価替えが行われます。
評価替えのタイミングで、土地の価格変動や建物の再評価などが行われ、固定資産税額が変動する可能性があります。
特に新築の場合、固定資産税の軽減措置(一般住宅の場合、新築後3年間は建物の固定資産税が2分の1に減額されるなど)が終了するタイミングや、最初の評価替えが行われる築6年目には固定資産税額が大きく変わるケースがあります。
また、築10年程度になると、建物の減価償却が進み、固定資産税が安くなる傾向が見られます。

売却を検討するなら?固定資産税も考慮して判断しよう
築50年の一戸建ての売却を検討する場合、固定資産税の負担も判断材料の一つとなります。
一般的に築年数が古い建物は、不動産の評価額が低くなるため、売却価格も低くなる傾向があります。
場合によっては、建物の価値がほぼ0円と評価されることも。
そのため、建物を解体して土地だけを売るか、現状のまま家付きで売るかなど、固定資産税の負担や将来的な活用方法も考慮して判断することが重要です。
固定資産税と相続

親から相続した一戸建てにも、固定資産税はかかります。
相続した場合の固定資産税の扱いや、相続税との違いを見ていきましょう。
相続した一戸建ての固定資産税はどうなる?
親などが所有していた一戸建てを相続した場合、固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれます。
相続が発生した年の固定資産税は、原則として亡くなった方が納税義務者となりますが、翌年度からは相続人が納税義務を負うことになります。
相続の手続きが完了したら、速やかに固定資産税の納税通知書送付先などを変更する手続きを行いましょう。
相続税と固定資産税、何が違うの?
相続税と固定資産税は不動産にかかる税金ですが、性質が大きく異なります。
相続税は、亡くなった方から財産を相続した際に、財産の総額に応じて一度だけ課税される税金です。
一方、固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を所有している限り、毎年課税される税金です。
相続税は国に納める国税であるのに対し、固定資産税は市町村に納める地方税です。課税対象となる財産の範囲や計算方法も異なります。
<<cta-private-01>>
固定資産税を安く抑えるには

固定資産税は毎年かかる費用なので、できるだけ安く抑えたいと考えるのは当然のことです。固定資産税を安く抑えるためのいくつかの方法をご紹介します。
建物を増やさない
固定資産税は、土地だけでなく建物にも課税されます。
そのため、必要以上に建物を増やすと、固定資産税の負担が増える可能性があります。
例えば、物置や車庫なども、基礎工事がされているなど一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税対象とみなされることがあるので注意しましょう。
固定資産税がかからない家はある?
原則として、土地や家屋などの固定資産を所有している限り、固定資産税はかかります。
ただし、固定資産の評価額が一定の金額以下の場合には、固定資産税が免除されることがあります。
免除基準は市町村によって異なるため、お住まいの地域の自治体に確認してみましょう。
また、新築住宅には固定資産税の軽減措置がありますが、税金が免除されるのではなく、一定期間、税額が減額されるものです。
リノベーション、リフォームによる減税
既存の住宅に対して特定の改修工事を行った場合、固定資産税の減税措置が適用されることがあります。この制度は住宅の性能向上を促進するためのものです。
適用条件や減額期間、割合などの詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
.webp)
耐震改修による固定資産税の減額措置
既存の住宅に対して特定の改修工事を行った場合、固定資産税が安くなることがあります。
例えば、耐震改修の場合、古い基準で建てられた家を、新しい地震に強い基準に合わせて改修すると、翌年から一定期間、固定資産税が減額されます。
このような減税措置を受けるには、工事後に自治体への申請が必要になることが多いです。
省エネ改修による固定資産税の減額措置
一定の省エネ性能を満たす改修工事(例えば、断熱改修や高効率給湯器の設置など)を行った場合も、固定資産税の減額措置が適用されることがあります。
改修後の省エネ性能が基準を満たすことや、工事費用が一定額以上であることが要件となる場合があります。減額期間や割合は自治体によって異なります。
バリアフリー改修による固定資産税の減額措置
高齢者や障がい者が居住する住宅で、手すりの設置や段差の解消などのバリアフリー改修を行った場合も、固定資産税の減額措置が適用されることがあります。
改修後のバリアフリー性能が基準を満たすことや、工事費用が一定額以上であることが要件となる場合があります。減額期間や割合は自治体によって異なります。
長期優良住宅化リフォームによる固定資産税の減額措置
住宅の長寿命化のためのリフォームで、所管行政庁の認定を受けた場合も、固定資産税の減額措置が適用されます。
耐震性、省エネ性、維持管理の容易性など、複数の項目で基準を満たす必要があり、減額期間や割合は他の改修工事よりも優遇される場合があります。
<<cta-private-01>>
リノベーションを考えているならフルリノ!で探そう
この記事では、固定資産税の基本的な知識から、築50年の一戸建てにかかる税金の目安、そして税金を安く抑えるための方法を解説しました。
特に、リノベーションは、住まいの性能を向上させるだけでなく、固定資産税の減税措置を受けることができる可能性があります。
リノベーションを検討する際には、様々なリノベーション会社を比較検討することが重要です。
フルリノ!では、あなたの理想のリノベーションを実現してくれる、信頼できる会社を簡単に見つけることができます。
リノベーションで失敗したくないなら、フルリノ!で多くの企業や事例を比較検討し、あなたのニーズにぴったりの依頼先を見つけましょう。
この記事が、あなたの住まいと税金に関する疑問を解消する一助となれば幸いです。
<<cta-consult-01>>









