「もっとおしゃれなキッチンにしたい」
「冬でも暖かいリビングが理想…」
そんなリノベーションの夢、費用を理由に諦めていませんか?
2025-2026年は、国や自治体の手厚い補助金で、ワンランク上の住まいを実現できる絶好のチャンスです。
この記事を読めば、複雑な制度の種類から申請方法まで、あなたの疑問が全て解決。
理想の家づくりを叶えるパートナー探しは、ぜひ『フルリノ!』にお任せください。
この記事でわかること
|
「フルリノ!」のLINE公式アカウントでは、補助金を賢く活用した素敵なリノベ実例や、理想の住まいづくりに役立つ情報を定期的に発信しています。
あなたの夢を叶えるヒントが満載ですので、ぜひこの機会に友だち登録をしてみてください。
<<cta-line-01>>
【2025年版】リフォーム・リノベーション補助金は?国と自治体の全制度を一覧解説
.webp)
2025年現在、リフォームやリノベーションで活用できる補助金制度は数多く存在します。
補助金制度は大きく「国の制度」と「自治体の制度」の2つに分けられ、条件が合えば併用することも可能です。まずは、どのような制度があるのか全体像を掴みましょう。
【国の制度】まずは知っておきたい主要な補助金・助成金
2025年に使えるリフォーム補助金は、主に国の「住宅省エネ2025キャンペーン」と、お住まいの自治体が独自に行う制度が中心です。
本章では、まず利用できる補助金の全体像を把握するために、国の主要な制度と自治体の制度を一覧で解説します。
【国の主要リフォーム補助金制度 比較表(2025年度)】
補助金制度の名称 | 主な対象工事 | 補助上限額(目安) |
住宅省エネ2025キャンペーン | 省エネ改修全般(断熱、高効率給湯器など) | 最大200万円以上 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 住宅の性能向上(耐震、省エネなど) | 条件により最大210万円〜300万円 |
既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 断熱材やガラス交換などの断熱改修 | 最大120万円 |
次世代省エネ建材の実証支援事業 | 高性能な断熱パネル・窓などの導入 | 事業費の1/2 |
介護保険における住宅改修 | バリアフリー改修(手すり、段差解消など) | 20万円 |
① 住宅省エネ2025キャンペーン
省エネ性能を高めるリフォーム・リノベーションを対象に、複数の補助事業をまとめて申請できる制度です。
2025年度の国の支援施策の中でも中心的な位置づけで、補助金の活用を考えているなら、最初に検討すべきキャンペーンです。
② 長期優良住宅化リフォーム推進事業
家の性能を総合的に高め、資産価値を向上させるための大規模リフォームを支援する制度です。耐震性や省エネ性の向上、三世代同居対応改修などが対象となります。
③ 既存住宅における断熱リフォーム支援事業
その名の通り、断熱性能の向上に特化した補助金です。高性能な断熱材を用いたり、窓を全て断熱改修したり、躯体全体の断熱工事を支援します。
④ 次世代省エネ建材の実証支援事業
次世代省エネ建材の実証支援事業は、まだ一般的に普及していない最先端の省エネ建材の導入を後押しするための制度です。
国が定めた高性能な断熱パネルや窓、調湿建材などの導入費用の1/2などが補助されます。
最先端の技術を取り入れたい方向けの専門的な補助金です。
⑤ 介護保険における住宅改修
要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの設置や段差の解消などのバリアフリー改修を行う際に利用できます。
制度自体は国が定めていますが、実際の申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口となる点に注意しましょう。
【自治体の制度】お住まいの地域独自の上乗せ・支援策

国の制度だけでなく、お住まいの都道府県や市区町村などの地方自治体も、独自の補助金制度を用意しています。
国の補助金に上乗せして支給されるケースも多く、併用すればさらにお得にリフォームが可能です。
まずは「〇〇市 リフォーム 補助金」のように「(お住まいの市区町村名)+(関連キーワード)」で検索してみましょう。
国と自治体の制度を併用して、最大額を受け取りたい方へ。WEB相談会なら、複雑な組み合わせもプロがシミュレーションします。あなただけの「一番お得なプラン」を無料で作成いたします。
<<cta-private-01>>
「住宅省エネ2025キャンペーン」を徹底解説【2025年度の目玉】

「住宅省エネ2025キャンペーン」は、「子育てグリーン住宅支援事業」「先進的窓リノベ」「給湯省エネ」の3つの補助金事業を、ワンストップで簡単に申請できる2025年度、注目の支援制度です。
本章では、それぞれの事業の対象工事や補助額を詳しく解説していきます。
① 3省連携のワンストップ申請で手続きが簡単に
「住宅省エネ2025キャンペーン」の魅力は、これまで別々だった国土交通省、経済産業省、環境省の補助金を一体で申請できる「ワンストップ申請」の仕組みです。
リフォーム・リノベ会社が手続きを代行するため、施主は複数の窓口に何度も書類を提出する必要がありません。
②子育てグリーン住宅支援事業|幅広いリフォームが対象
高い省エネ性能を持つ住宅を増やすことを目的とした制度です。2025年の制度では、これまでの「子育て・若者夫婦世帯」への優遇は維持しつつ、全ての世帯が対象となりました。
窓や壁の断熱改修などが必須ですが、それを満たせば食洗機の設置なども対象に含められます。
https://furureno.jp/magazine/renovation-parenting-generation-renovation
③ 先進的窓リノベ2025事業|窓・ドアの断熱改修に特化
熱の出入りが多い窓やドアの断熱性能向上に特化した、補助率が高い制度です。
内窓の設置や外窓の交換などが対象となり、工事費用の1/2相当など、国が重点的に支援を行っているため補助額が大きいのが特徴です。
https://furureno.jp/magazine/renovation-subsidy-guide-window
④ 給湯省エネ2025事業|高効率給湯器の導入を支援
エコキュートやハイブリッド給湯器などの高効率な給湯器への交換費用を補助する制度です。日々の給湯にかかるエネルギー消費を抑えたい方におすすめです。
長期利用・断熱・介護・空き家活用で使える国の補助金制度

「住宅省エネキャンペーン」の対象外でも、家の性能向上(長期優良住宅化)や介護のためのバリアフリー改修、空き家の活用などの目的であれば、別の補助金を利用できる可能性があります。
本章では、特定の目的に特化した補助金制度を解説します。
① 長期優良住宅化リフォーム推進事業|家の資産価値を高める
住宅の寿命を延ばし、資産価値を高めるための性能向上リフォームを支援する制度です。補助金だけでなく、固定資産税の減額などの税制優遇も受けられるのが大きなメリット。
ただし、リフォーム後も住宅を長期的に維持していくための「維持保全計画」の策定などが必須となります。
② 既存住宅における断熱リフォーム支援事業|夏の暑さ・冬の寒さを解消
高性能な断熱材や窓を用いて、躯体全体を“丸ごと”断熱するような本格的なリフォームを支援します。
家全体の温度差を解消し、冬場のヒートショック対策にも繋がるなど、健康リスクを低減する効果も期待できます。
出典:公益財団法人北海道環境財団:【全国対象】既存住宅の断熱リフォーム支援事業
③ 介護保険における住宅改修|バリアフリーリフォームを支援
要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの設置や段差解消などのバリアフリー改修を行う際に利用できます。
自己負担は原則として費用の1割(所得により2〜3割)で済むのが特徴です。
要介護度に関わらず上限は20万円ですが、転居した場合や、介護度が3段階以上重くなった場合には、再度利用できます。

④ 空き家・実家のリフォームで使える補助金
社会問題化している空き家の活用を促進するため、国や自治体は様々な支援を用意しています。
国の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、空き家を改修する場合の補助額が上乗せされることがあります。
また、各自治体も移住・定住促進などを目的に独自の補助金制度を設けている場合が多く、手厚い支援が期待できます。
空き家リノベーションの補助金一覧|国・自治体の制度や成功事例も紹介
【結局いくらもらえる?】リフォーム内容別の補助金シミュレーション
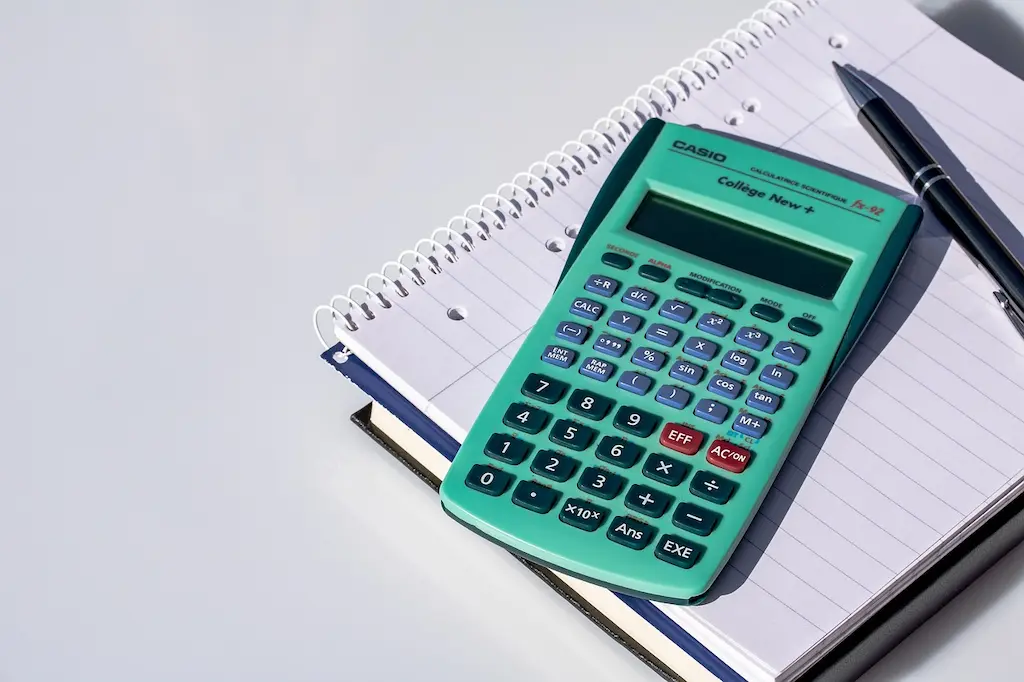
補助金は、複数の制度を組み合わせることで、合計で数十万円以上お得になるケースも少なくありません。
本章では、具体的なリフォーム内容を想定し、補助金額がいくらになるのかをシミュレーションします。
モデルケース①:戸建て住宅で、リビングの断熱リフォームを行った場合
冬の寒さが厳しいリビングを快適にしたい、という目的で断熱リフォームを行った場合のシミュレーションです。
【合計補助額】約421,000円 |
モデルケース②:子育て世帯が、マンションで水まわりを中心にリフォームした場合
子育てを機に、古くなったマンションの水まわり設備を一新し、省エネ性能も高めたい場合のシミュレーションです。
【合計補助額】約134,000円 |
モデルケース③:築30年の戸建て住宅で、家全体の断熱性能を抜本的に向上させた場合
夏の猛暑と冬の厳しい寒さ、そして高騰する光熱費に悩み、家全体の快適性と省エネ性能を最大化する目的で、大規模な断熱リフォームを行った場合のシミュレーションです。
工事内容:
補助金額の試算(例):
【合計補助額】2,272,000円 |
このように、リフォーム全体を「窓」「壁」「給湯器」などの工事内容に分解し、それぞれに最適な補助金制度を当てはめていくのが、制度活用のコツです。
特に「住宅省エネ2025キャンペーン」は、複数の制度を組み合わせられるため、有用な制度です。
ただし、どの組み合わせがベストかは専門的な知識も必要になるため、まずは補助金制度に詳しいリフォーム・リノベ会社に相談してみましょう。
<<cta-consult-01>>
【リフォーム箇所別】あなたの工事で使える補助金をチェック

ここまで様々な補助金制度をご紹介しましたが、「結局、自分の場合はどれ?」と迷ってしまうかもしれません。
本章では視点を変え、「やりたいリフォーム工事」を主役に、それぞれ関連性の高い補助金制度を整理して解説します。ご自身の計画に合う項目からご覧ください。
窓・ドア・壁などの断熱リフォーム
家の快適性や光熱費に大きく影響するのが断熱性能です。
特に熱の出入りが激しい窓やドアの改修は「先進的窓リノベ2025事業」が高い補助率で対応しており、優先的に検討すべき制度です。
壁・床などの断熱工事は「子育てグリーン住宅支援事業」がカバーしています。
断熱性能を高めるリノベーション・リフォーム~一年を通して快適な住宅を作ろう~
キッチン・お風呂・トイレの水まわりリフォーム
毎日の暮らしを快適にする水まわり設備も、省エネ性能の高い製品を選ぶことで補助金の対象となります。
高断熱浴槽、節水型トイレ、節湯水栓などの導入は、主に「子育てグリーン住宅支援事業」でカバーされます。高効率給湯器への交換は「給湯省エネ2025事業」が利用できます。
また、三世代同居のためにキッチンを増設する場合などは「長期優良住宅化リフォーム推進事業」も利用できる可能性があります。
水回りリノベーション・リフォームの費用相場は?セットプランや注意点を徹底解説
手すり設置・段差解消などのバリアフリーリフォーム
ご家族が安全に暮らすためのバリアフリー改修には、心強い支援制度があります。
要介護・要支援認定を受けている方がいる場合は、自己負担1割(所得により変動)で工事ができる「介護保険における住宅改修」が選択できます。
対象となる工事は手すりの設置、段差の解消、引き戸への交換などです。
それ以外のご家庭でも「子育てグリーン住宅支援事業」で手すりの設置や段差解消が対象となっています。
バリアフリーリフォーム・リノベーションとは?車椅子に適した工事と費用相場を解説
申請から入金までの流れ|いつまで?いつもらえる?

補助金の申請は、①情報収集・相談 → ②交付申請・契約 → ③工事・完了報告 → ④審査・入金、という4つのステップで進むのが一般的です。
特に、工事契約の前に申請が必要な点と、補助金は後払いである点に注意が必要です。本章で、具体的な流れを解説します。
STEP1:情報収集と相談(どの補助金が使えるか調べる)
まずは補助金制度に詳しいリフォーム・リノベ会社に相談し、自分の計画でどの補助金が使えるか、いくらぐらい補助されそうかの診断と提案を依頼しましょう。
STEP2:交付申請と工事契約(契約前に申請するのが鉄則!)
利用する補助金が決まったら、事業者を通じて事務局へ交付申請を行います。原則として、補助金の交付が決定した後に、事業者と工事の契約を結びます。
契約後の申請は対象外となるケースがほとんどなので、順番を間違えないようにしましょう。
STEP3:工事の実施と完了報告
交付決定後、工事を開始します。補助金ごとに定められた期限内に工事を完了させる必要があります。
工事が終わったら、内容を証明するための書類や写真を事業者が事務局へ提出(完了報告)します。
STEP4:審査完了と補助金の入金
完了報告が受理され、審査が終わると、補助金が交付(入金)されます。完了報告から入金までは数ヶ月の審査期間を要するのが一般的です。
補助金は後払いであり、一旦はリフォーム費用を全額支払う必要がある点に注意しましょう。
リフォーム補助金申請のよくある失敗例と回避策

補助金がもらえなくなるよくある失敗は、以下の4つです。
- 契約後の申請
- 予算上限による締切
- 対象外の工事・製品の選択
- 書類の不備
本章では、失敗を未然に防ぐための具体的な回避策を専門家が解説します。
失敗例①:工事の契約後に申請してしまった
特に多い失敗例です。補助金は、あくまで「これから行う工事」に対して交付されるため、契約済みの工事は原則として対象外です。
【回避策】
リフォーム会社への相談を始める際、まずは「補助金を利用したい」と明確に伝え、申請の段取りやスケジュールを確認しましょう。
失敗例②:申請期間内なのに「予算上限」で締め切られた
国の大型補助金は、申請期間の終了を待たずに、申請額が予算の上限に達した時点で受付を締め切ります。
【回避策】
「まだ期間があるから大丈夫」と油断せず、早めの情報収集と申請を心がけましょう。信頼できる事業者に相談し、制度が始まったらすぐに動けるように準備しておくことが重要です。
失敗例③:対象外の工事・製品を選んでしまった
補助金には、対象となる工事内容や製品の性能(断熱性能など)に細かな規定があります。
自分で選んだ製品が、実は補助金の基準を満たしていなかったケースも少なくありません。
【回避策】
対象製品や工事内容が公募要領に適合しているか、事業者とカタログなどでダブルチェックを徹底しましょう。
失敗例④:必要書類の不備で審査に落ちた
申請には、本人確認書類や工事の証明書など、多くの書類が必要です。一つでも不備があると、審査に落ちたり、手続きが大幅に遅れたりする原因になります。
【回避策】
多くの補助金は事業者による申請代行が基本です。実績豊富なプロに任せ、チェック体制を万全にして臨みましょう。
補助金の相談はどこにすべき?それぞれの相談先の特徴を解説

補助金の相談先は、計画から申請まで一貫して任せられる「リフォーム・リノベ会社」と、正確な制度内容を確認できる「自治体の担当窓口」の2つが主です。
リフォームと補助金活用をスムーズに進めるには、まず事業者に相談するのが効率的です。
計画から申請までを一貫してサポートする「リフォーム・リノベ会社」
リフォームや補助金のことで悩んだ時、身近で頼りになる相談相手が、リフォーム・リノベ会社です。
彼らは補助金活用のプロでもあるため、あなたの計画に最適な国・自治体の制度を提案し、補助金を活用した費用対効果の高いプランを設計してくれます。
さらに、複雑な申請手続きの代行まで一貫してサポートしてくれるため、計画から工事までをワンストップでスムーズに進めたい場合の、確実で効率的な相談先です。
<<cta-consult-01>>
正確な制度内容を確認できる「自治体の担当窓口」
お住まいの市区町村が実施している独自の補助金制度について、正確で詳細な情報を得られるのが自治体の担当窓口です。
公式サイトでは分かりにくい細かな条件や、最新の予算状況などを直接確認できます。
ただし、窓口の役割はあくまで制度内容の説明であり、申請書類の作成サポートや、リフォーム工事そのものの相談はできない点に注意しましょう。
【補助金だけじゃない】リフォーム費用を抑える「減税制度」と「ローン」の知識
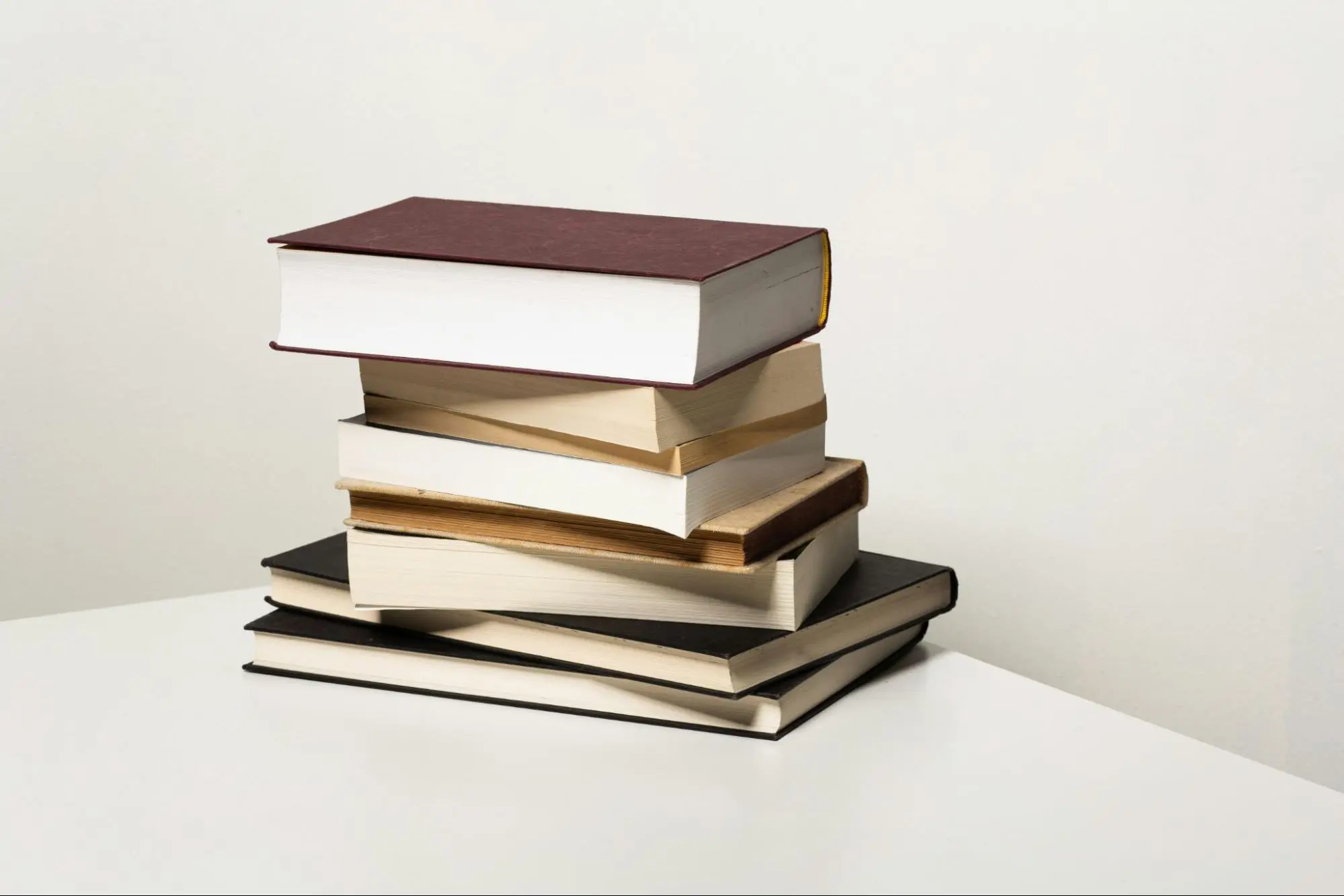
リフォーム費用を抑える方法は、補助金だけではありません。
税金の負担が軽くなる「リフォーム減税制度」や、低金利で資金を借り入れできる「リフォームローン」も重要な選択肢です。
補助金と併用できる場合も多いため、合わせて確認しておきましょう。
「リフォーム減税制度」
省エネ、バリアフリー、耐震など、特定の性能向上リフォームを行った場合、所得税や固定資産税が控除される制度です。
所得税の控除には、工事費の一部が直接税額から差し引かれる「税額控除」があり、大きな節税効果が期待できます。
「リフォームローン・融資制度」
リフォーム費用を借り入れる際に、優遇金利が適用される制度もあります。
代表的なものに、住宅金融支援機構の【フラット35】リノベがあり、中古住宅の購入とリフォームをセットで行う場合などに金利の引き下げが受けられます。
【速報】2026年も「住宅省エネ2026キャンペーン」実施決定!

令和7年(2025年)11月28日、政府より「住宅省エネ2026キャンペーン」の実施方針および予算案が閣議決定されました 。
国土交通省・環境省・経済産業省の3省が連携し、家庭の省エネ化を強力に推進します 。
最大のポイントは、令和7年11月28日以降に工事着手したものが対象になる点です 。
2025年の制度から空白期間なくスムーズに新制度へ移行できるため、リフォームのタイミングを逃す心配がありません。
1. 【省エネ・躯体】みらいエコ住宅2026事業(国土交通省)
これまで「子育てエコホーム支援事業」として親しまれてきた制度の後継として、「みらいエコ住宅2026事業」が始まります。
リフォーム分野においては国土交通省が主体となり、開口部や躯体(壁・床・天井)の断熱改修や、エコ住宅設備の設置を支援します 。
また、これらの必須工事とセットで行うことで、子育て対応改修やバリアフリー改修も補助の対象となります 。
補助額は「リフォーム前の家の性能」と「リフォーム後の性能」の組み合わせによって上限が決まる仕組みに変更されました 。
【リフォームの補助上限額】
リフォーム前の住宅性能 | リフォーム後の性能(目標) | 補助上限額 |
平成4年基準 を満たさない | 平成28年基準 相当へ | 100万円/戸 |
平成11年基準 を満たさない | 平成28年基準 相当へ | 80万円/戸 |
平成4年基準 を満たさない | 平成11年基準 相当へ | 50万円/戸 |
平成11年基準 を満たさない | 平成11年基準 相当へ | 40万円/戸 |
3つの省エネ基準とは?(築年数は目安)
平成4年基準未満(〜1991年頃)
「ほぼ無断熱」の家です。断熱材が入っていない、または極めて少なく、外気の影響を直接受けるため「夏は暑く、冬は極端に寒い」のが特徴です。
平成11年基準未満(〜1998年頃)
「断熱が不十分」な家です。多少の断熱材は入っていますが、現在の基準に比べると薄く、窓も単板ガラスが主流で、快適とは言えません。
平成28年基準
「現代の快適な新築」レベルです。壁や天井に十分な厚みの断熱材が入り、窓も複層ガラスなどが使われ、冷暖房効率が良く快適に過ごせます。
2. 【窓・断熱】先進的窓リノベ2026事業(環境省)
窓リフォームに特化した人気制度は、「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(通称:先進的窓リノベ2026事業)」として継続します 。
高断熱窓(熱貫流率Uw1.9以下など)へのガラス交換・内窓設置・外窓交換が対象で、工事内容に応じた定額が補助されます 。
注意点ですが、補助上限額は2025年度の200万円から変更され、1戸あたり最大100万円となりました 。
上限額は変わりましたが、依然として高い補助率が期待できる制度であることに変わりはありません。
3. 【給湯器】給湯省エネ2026事業(経済産業省)
高効率給湯器の導入を支援する「給湯省エネ2026事業」も継続されます 。 主な補助額は以下の通りです 。
- ヒートポンプ給湯機(エコキュート):10万円/台
- ハイブリッド給湯機:12万円/台
- 家庭用燃料電池(エネファーム):17万円/台
※寒冷地で電気温水器などを撤去する場合には、加算措置も用意されています 。
さらに新制度として「賃貸集合給湯省エネ2026事業」が創設されました 。
既存の賃貸集合住宅において、従来型給湯器を小型の省エネ型(エコジョーズ等)へ取り替える場合、以下の通り補助されます 。
- 追い焚き機能なし:5万円/台(※ドレン排水ガイド工事を行う場合は8万円/台)
- 追い焚き機能あり:7万円/台(※浴室へのドレン排水工事を行う場合は10万円/台)
いつから対象?
令和7年(2025年)11月28日以降に対象工事に着手した案件が、新キャンペーンの対象となります 。
すでに新制度の実質的な対象期間に入っていますので、予算がなくなる前に、早めの計画と申請準備を進めましょう。
※本情報は閣議決定された補正予算案に基づくものであり、今後国会での成立が前提となります 。
国土交通省:住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定
新しい2026年キャンペーンの対象になるか不安な方は、専門家に確認するのが一番です。オンライン相談で、最新の制度に基づいた対象工事やスケジュールを、プロが丁寧に診断します。
<<cta-private-01>>
【ルームツアー動画】補助金を賢く活用!築40年鉄骨住宅リノベーション実例
百聞は一見にしかず。補助金を活用したリノベーションが、どれほど暮らしを変えるのか、実際のルームツアー動画でご覧ください。
今回ご紹介するのは、築40年の鉄骨住宅です。冬の寒さという課題を、国の「先進的窓リノベ事業」などの補助金を活用した断熱改修で解決。
趣味のサウナや愛猫との暮らしを妥協なく楽しむ、快適な空間を実現しました。全貌を、ぜひ動画でご体感ください。
この事例を担当したのは、アズ建設です。事例のようなリノベーションを希望している方は、ぜひお気軽にアズ建設へご相談ください!
<<cta-builder-consultation-17>>
まとめ:補助金を賢く活用し、後悔しないリフォーム・リノベーションを
本記事では、2025年度に活用できる国の大型キャンペーンから、お住まいの地域独自の制度、申請の流れ、そしてよくある失敗例まで、リフォーム・リノベーションの補助金に関する情報を網羅的に解説しました。
補助金制度は複雑に見えますが、良い住まいづくりを目指す皆さんを国や自治体が応援してくれる、心強い制度です。
正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーと連携すれば、金銭的な負担を大きく軽減しながら、理想の住まいを実現できます。
補助金を活用した本格的なリノベーションで失敗したくないなら、複数の企業や施工事例を比較検討し、信頼できるパートナーを見つけることが不可欠です。
豊富なリノベーション事例の中から、あなたの理想に近い住まいを探せる「フルリノ!」で、後悔しない家づくりの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
<<cta-info-01>>









